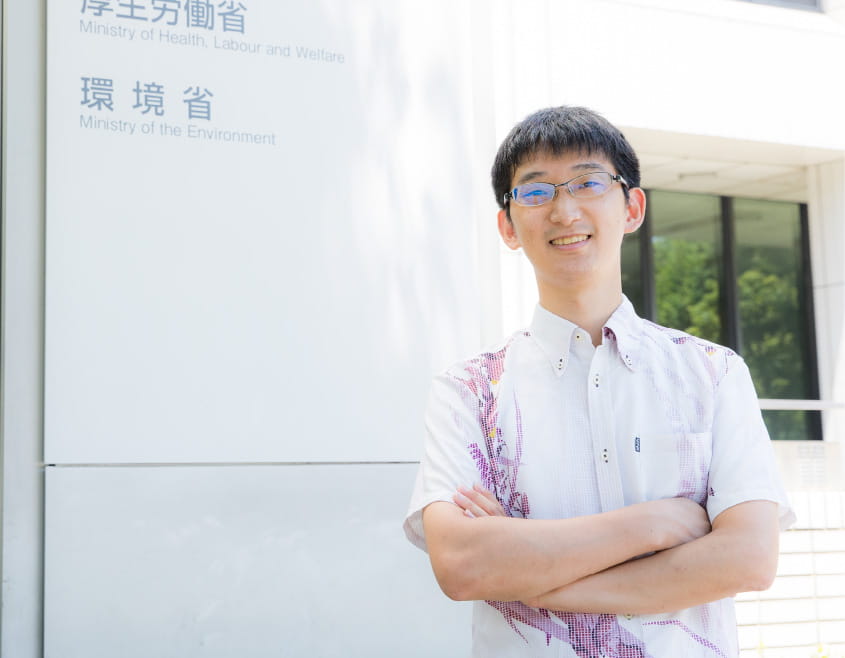Profile
卒業生/OB/OG
村井 辰太郎さん
環境資源工環境資源工学科
2014年 修士卒業
VOL.7
Profile
卒業生/OB/OG
村井 辰太郎さん
環境資源工環境資源工学科
2014年 修士卒業
大学時代に躓いた経験、
それが人生の大きな転機に。
私たちの世代ぐらいから、「環境」問題がテレビや新聞で多く取り上げられ、例えば中学時代にはワンガリ・マータイさん(ケニアの政治家。ノーベル平和賞受賞)の「もったいない運動」(※)が話題になっていました。こうした活動など、環境問題について接する機会が中高時代から多くあったので、リサイクルなどの社会課題に自然と興味を持ち、もっと詳しく知りたいと思い環境資源工学科を進学先に選びました。(※)日本語の「もったいない」という言葉を世界に広げ、ものを大事にする精神を広げようという運動。
大学1,2年生時は、いわゆる“大学生活”を楽しんでしまい、サークルやアルバイトに力を入れた結果、お世辞にも勉強に力を入れたとは言えないような生活を送っていました(笑)。実は、そうした影響もあってか、必修を一単位だけ落としてしまい、3年生に留年をしてしまいました。当時はショックを受けましたが、この出来事が良い意味で人生の大きな転機になったと振り返ってみると感じています。
留年したことで、一度立ち止まり自分が将来何をしたくて入学したのかを改めて考える時間ができ、初心を取り戻し、やはり環境問題に関わる仕事がしたいという気持ちを強く持ちました。ちょうどその時、国家公務員になった高校の先輩がから話を聞く機会があり、仕事のやりがいなどを教えて貰った結果、環境省に就職するという選択肢を意識するようになりました。幸い自分には時間があったので公務員試験の勉強し、大学4年時に合格をしましたが、筆記試験後の面接に進める権利は合格から2年間保持できるため、一度大学院に進学し、研究活動に専念することにしました。

一国に留まらない「越境大気汚染」。
「世界と交渉して解決したい」。
大学4年生になり、香村研究室に入りました。香村先生は土壌環境が専門で、現場を重視されており、生徒が自らフィールドワークを行うことの重要性を教えていただきました。研究室のメンバーも皆活発に研究活動を行っており、ゼミの後にも一緒に鍋をつつくなど、3年間とてもよい雰囲気で研究室生活を過ごすことができたと感じています。
私は、ため池の底にある土(底質)を掘って分析することで過去の大気汚染を調査する研究をしていました。底質を調べていくと、下から時系列順に堆積するため、その分析結果をグラフにすることで、過去にどの程度の大気汚染があったのかという推移が分かります。また、汚染物質の特徴を更に分析することで、どこから飛んできたかということも推測でき、結果、日本国外からの影響を観測することに成功しました。
こうした越境大気汚染の研究をしていると、日本だけで対策を行っても環境問題は解決しないため、国際的な枠組みやルールを決めて進めなければ行けないという問題意識持つようになりました。それを実現には、国という立場で仕事をして、世界と交渉するのが一番効果的であるという思いから、大学院を修了後、環境省に入ることを決めました。
自分が決めたことが、
国の方針になることへの責務。
環境省では、これまで5つの部署を経験しました。入省して配属された温暖化国際交渉の部署ではパリ協定の交渉を裏方で支え、2、3年目には、福島の除染の部署で、除染に必要な予算の折衝などを担当しました。
次に、環境アセスメントの部署では、風力発電や火力発電などの建設に関する事前審査を行いました。例えば、風力発電の審査では、この場所は渡り鳥の通り道だから、建設地はちょっとずらしたほうがいいなど、人間の生活環境だけにこだわらず、動植物などの環境に対する配慮・検討も行いました。
その後、語学力を伸ばし、行政について体系的に学びたいと思い、国家公務員の研修制度を利用し、フランスに2年ほど留学しました。
フランスで感じたのは、ヨーロッパは環境分野においては、日本と比べると人々の意識が高く、先進的な政策が多いという点でした。例えば飛行機の短距離フライトを温暖化の観点から禁止するなど、今の日本だとほぼ考えられない対策ばかりで驚きました。
留学先から帰国した現在は、プラスチックのリサイクルに関する部署で働いており、従来の大量生産・大量消費から資源を循環させる「サーキュラーエコノミー」への移行を目指し、新しいリサイクル制度の策定に携わっております。
どの部署でも共通することですが、環境省は人数が少ないことから、若い頃から政策立案に携わるチャンスが多いということです。ただし、その分自分の意見が国の方針になる可能性も高く、責任感を持ちながら働くことが求められるのが重要だと考えています。
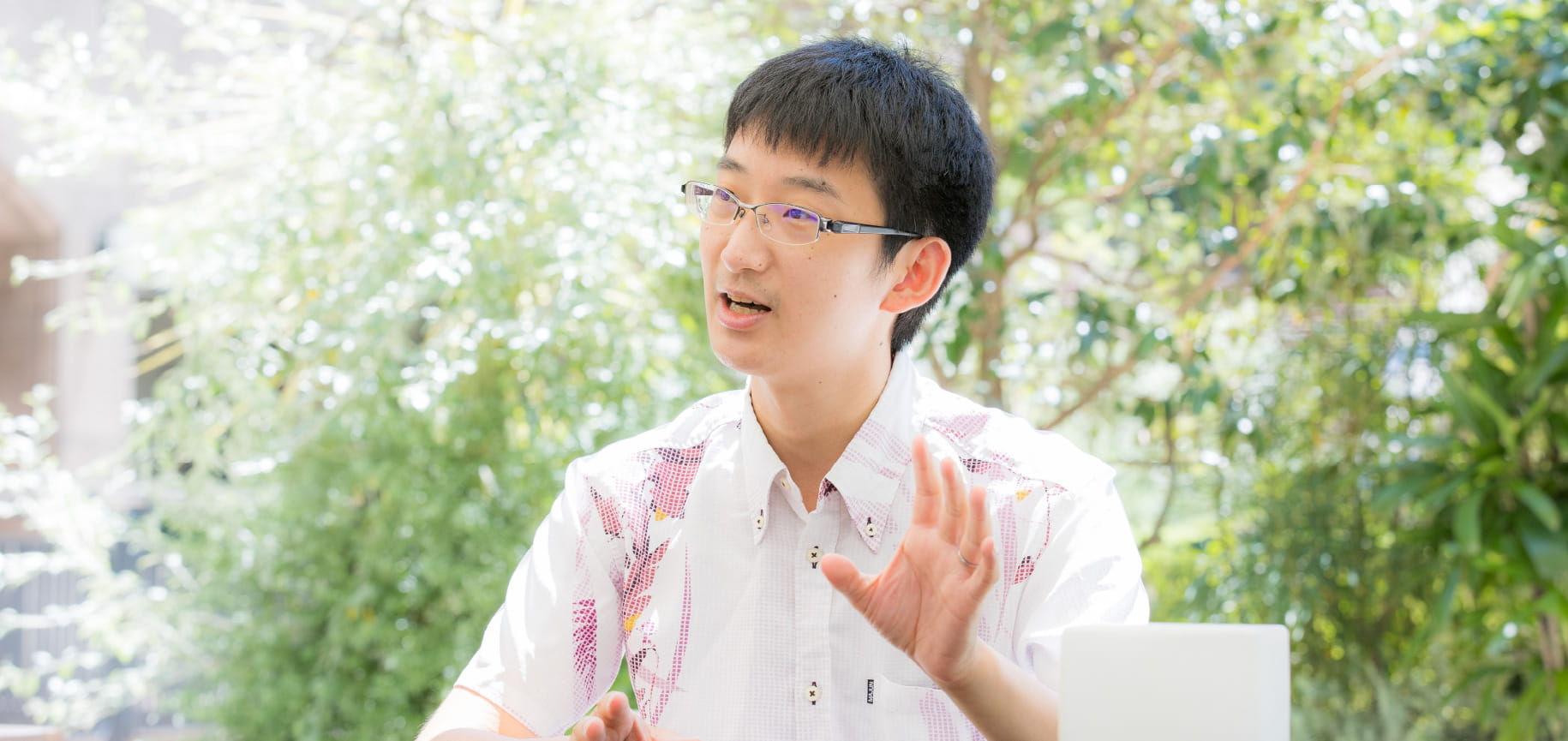
幅広く学び、多角的な視点を養った経験が社会でも役立つ。
環境資源工学科は、幅広い内容の講義があり、1つの学科にいながら、多角的な視点を得られることが出来ると思います。環境、資源循環、素材、石油・資源など多様な専門分野が選べ、そのようなバックグラウンドがあるからこそ、日々の仕事や留学先での研究などにおいても、有利にはたらくことがあると実感しました。
また、大学で出会った人々とのご縁も非常に重要でした。私が環境分野で働いているからかもしれませんが、仕事でお付合いのある企業や団体に所属している方々の中に環境資源工学科のOB・OGが多くおり、その場合は仕事がしやすく、この学科を卒業して良かったと感じます。
“持続可能な地球”への展望。
SDGsという言葉が一般に浸透してきた現在、その土台となる「環境問題」はますます注目を浴びております。今ではニュースで環境問題が取り上げられない日が一日もないと実感するほどです。また、他にも2021年の成長戦略に掲げる柱の一つに「グリーン分野」が位置づけられるなど、日本政府としての力の入れぐらいも年々強化されています。
こうした環境・エネルギー分野に関する選択肢は幅広く、学科のHPに掲載されているOB、OGの就職実績を見てれば分かると思います。また、これからも重要性が増し、確実に伸びて来る分野の一つですので、もし、高校3年生で進路が決まっていないのであれば、ぜひ、環境資源工学科で学ぶことをおすすめします。日本の、世界の「環境」の将来を共に変えるために一緒に働ける日を楽しみにしております!